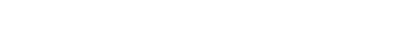コロナ禍に伴い、ソーシャルディスタンスの厳守や移動制限などで、マスコミの取材方法も激変しました。実際に会って進める対面のインタビュースタイルが大幅に使えなくなり、Zoomをはじめとしたオンライン会議システムやSkypeなどのビデオ通話スタイルでのインタビューがぐっと増えました。また、記者会見では、透明のアクリル板がマイクの前に設けられることが当たり前になっているほか、囲み取材も大幅に距離を取らざるを得なくなりました。さらに、海外や地方への出張取材などでも、影響とそれに伴う変化が出ています。今回はコロナがもたらした取材方法の変化について、その長短と将来を考察します。

コロナ禍での取材を取り巻く現状
メディアが参加する記者会見の様変わりは至る所に及んでいます。例えば、リアルで開催する場合、省庁や経済団体の会見は、その多くが通常の会見室や会議室からひと回り広い、講堂やホールに変更になっています。また、会見終了後や通称「ぶら下がり」と呼ばれる「囲み取材」についても、会見者と記者の間に“規制線”が敷かれるなど、一定の距離がとられています。もっとも、最近は、囲み取材そのものを見合わせるケースも出始めていて、使用するマイクも終了後、アルコールによる消毒を施しています。さらに、会場を変更しない場合は、「1社1名」「代表取材」のように、会場へ入る人数を制限する形も取られるようになりました。たずさわるスタッフや出演者もマスクは使えないので、フェイスガードの装着が当たり前になっています。こうした現状の下、各社はリモート取材をうまく活用し、リアルな取材の代用にしています。
リモート取材のメリット・デメリット
こうした中で、いわゆるリモート取材の効果が最大限、発揮されているのが、遠隔地の取材です。国内取材でもこれまでは、記者やディレクターがカメラマンを従えて、直接、現地へ赴き、収録するのが一般的でしたが、オンライン取材の普及で、スマホとインターネットの環境さえあれば、SNSなどを通じて、取材交渉し、ゴーサインが出た後、取材を始められるようになりました。当然、移動時間と費用の節約にもなるので、いまや、報道・情報番組で、リモートインタビューを観ない日はありません。加えて、普段は取材交渉が難しい相手だとしても、オンライン取材であることをアピールすれば、収録先へ出向く必要がなく、自宅や勤務先で気軽に出演できるので、取材を前向きに検討してもらえる可能性が高まります。
現に、地方局などでは、海外や在京の学識経験者などへのインタビューに、リモート取材を頻繁に活用し、ローカルニュースやワイド番組での情報の充実を図っています。
制作側からすれば、従来の電話出演が「映像付き」になった感覚といえるでしょう。
一方で、海外や地方の映像が欲しいときは、ロケハンなどを省いて、SNS上で映像を募集したり、その土地在住の知り合いに代わりに撮影を依頼したりするなど、各番組とも、工夫しながら映像素材を集めるようになりました。この他、小規模な会見などであれば、会場を押さえる必要が無くなり、コスト削減につながるのをはじめ、指定のURLさえ公開すれば、報道機関だけでなく、一般人にも質問の機会が与えられるので、門戸開放としては大変有効です。
こうした環境下ですから、当然、オンラインならではの取材テクニックも徐々に開拓されてきています。例えば、通信環境の事情で、どうしても会話にタイムラグが生じますので、自分の話したことが、実際に相手の耳へ届くまでには、想定よりも時間がかかることを頭に入れながら会話しないと、スムーズさに差が出てしまいます。また、画面越しで、対面取材に比べてどうしても表情が読み取りにくくなるため、対面で取材するときよりもリアクションは少しだけオーバーにすることも、取材を円滑に進めるポイントの一つといって、良いでしょう。バラエティ番組で芸人さんやタレントさんがよくやっている、いわゆるワイプ芸などは参考になりそうです。
ただ、このリモート取材もメリットばかりではありません。現場の取材記者からは、記事の内容にも影響が出ているという声があがっています。例えば、有名人をインタビューする場合、直接、会いに行けば、職場の様子や本棚の本、コーヒーを飲む時の視線の先などがわかり、それらも描写することで人物をより深く表現できますが、多くの場合「撮りきり」の画になってしまうので、その空気感を感じることは難しくなります。また、政治家や警察官に密着して内部の極秘情報をとる「アクセスジャーナリズム」という取材手法がとりにくくなり、政治や行政といった権力が隠しておきたい秘密を暴きづらくなるので、リモート取材が当たり前にされてしまうのは、民主主義にとってよくないと指摘する意見もあります。そもそも取材対象がネットユーザーに限定されてしまいますので、相手がどのくらいインターネットやカメラのオペレートに慣れているか、取材前のリサーチが不可欠です。ZoomやSkypeなど、ツールの共有確認も欠かせません。また、首尾よく、相手がネット環境に習熟していたとしても、対面に比べて、親近感がわきづらく、名刺交換などのネットワーキングの時間がないことも、これまでの商慣習とは違うので、注意が必要です。
さらに新たなハードルとして、5~6人以上のグループインタビューは、工夫しないと難しい場合があります。1対1の取材は問題ないとしても、オンラインでグループインタビューを行う場合は、基本的にインタビュアーがしっかりタイムキープをしながら、全員に等しく発言してもらうよう場を回すことが肝心です。こうした課題に通底していえるのは、多くの取材シーンで、普段、リモート撮影に慣れていないカメラマンが、ワンマンでオペレートし、行き届いた映像の撮影が、かなり厳しくなることです。仮にワンマンで取り得る限りの対策を取ったとしても不慣れな撮影では、例えば、商品発表会で、肝心の新商品を間近で観察できなかったり、経営陣や商品担当者と直接やりとりできなかったりするなど、限界を感じる場合もあるでしょう。

リスク軽減のためにもプロへの依頼を
回線容量による遅延は、通信環境の問題も絡むので、致し方ない部分もありますが、例えば、カメラマン不足の解消や、質の高いインタビューを求めるのなら、プロへ依頼するというのも、一考です。プロであれば、映像の切り替えや音声の調整といった作業は経験豊富ですし、リモート取材の経験値も高くリスクははるかに少なくて済みます。仮にトラブルがあっても、プロであれば、対処する「引き出し」を何通りも持っているので、安心して任せられます。何よりも「高い技術力」で、先述の「取材の際の空気感の喪失」といった懸念材料の軽減も期待できるでしょうし、機材のことを気にせずに、インタビューに専心して応じられます。もし、メディアから、取材依頼があった場合、カメラワークは、プロへの依頼を検討してみるのも、良い選択肢かも知れません。と同時に、コロナによる「ニュースタンダード」で、取材する側、受ける側の心構えが大きく変わる中、映像市場の拡大は今後、ますます拡がりを見せそうです。
テキスト:ナインフィールド
プロデューサー 笹木 尚人