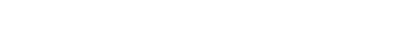視聴率、ラジオでいう聴取率は言うまでもなく、放送局の経営を語る上で外せません。数字が高いほど、広告媒体としての放送の価値は上昇します。結果、収入の増大をもたらし、局の利益拡大に貢献します。よって、どの民間放送も視聴率の動きには敏感にならざるを得ません。今まではテレビは家族でみるものとして世帯視聴率が主でしたが、世帯人数が減っている影響もあって、個人視聴率の評価が主流になりつつあります。
今回は部署を問わず、全てのテレビマンが逃れられない「視聴率」の仕組みと今後の展開について、探っていきます
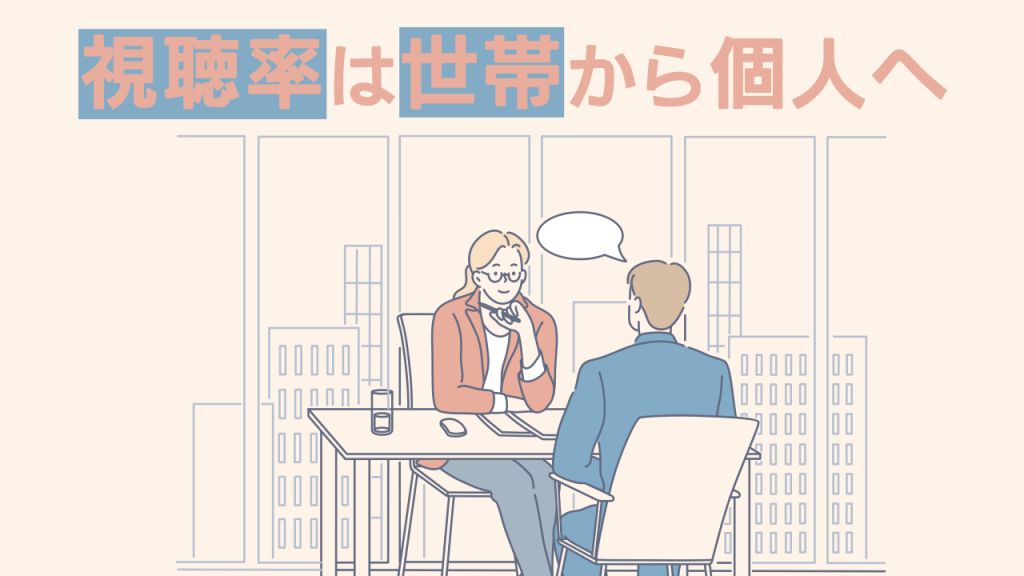
世帯視聴率と個人視聴率
視聴率には「世帯視聴率」と「個人視聴率」の2つの種類があります。世帯視聴率は調査の最小単位を「世帯」として、ある番組を視聴する世帯の割合を示した数値です。これに対し、個人視聴率は世帯内で、「4歳以上の家族全員」の内、誰がどのくらい番組を視聴したかを現します。調査世帯数は全国32地区、1万世帯で、内訳は関東が2700、関西が1200、中京が600、札幌と福岡がそれぞれ400、そのほかの地区が200ずつとなっています。調査は、総合視聴率と個人視聴率を同時に調査できるピープルメーターというシステムが導入され、世帯当たり、最大8台のテレビに取り付けられた機器で視聴番組を調査し、翌朝、オンラインでデータセンターへと送信されます。また民放が2局以下のエリアでは、日記式によるアンケート調査も併用されています。
個人視聴率のしくみと導入の背景
もともと視聴率の調査は、世帯視聴率からスタートしました。しかし時代とともに、一家団欒でテレビを楽しむスタイルから、個人が各々の部屋で好みの番組を視聴するスタイルに変化してきました。一方で、スポンサーとしては、商品を広告するのに、その商品を購入してくれる層にメッセージを発信したいので、世帯という大雑把な括りではなく、どのような個人が番組を観ているのかが関心事になってきました。個人視聴率が導入された背景には、こうしたライフスタイルの変化が挙げられます。
個人視聴率は初め、日記式のアンケートから始まりました。これは対象世帯全員に調査票を配り、世帯内の対象者全員が、調査票に5分単位で、視聴状況を記録。1週間ごとに調査員が回収し、集計します。しかし、この方法だと調査を依頼する側も、協力する側も大きな負担になってしまうため、ピープルメーター(=PM)というシステムが導入され、機械式での調査が始まりました。この装置には、家族全員に番号が割り当てられ、テレビの視聴開始時と終了時に、リモコン上で自分の番号のボタンを押します。視聴データは翌朝早くに電話回線を通じて、データセンターへ転送されます。この方法ですと、協力側の負担も軽減できますし、一つの番組を何人で見ていたかが集計できるので、個人視聴率の1位が、1番多くの人に観られていた番組という結論になります。
タイムシフト視聴率導入の背景
これまで、「世帯視聴率」「個人視聴率」を紹介してきましたが、これらはともにリアルタイムでの調査です。しかしながら、録画で番組を楽しむなど、テレビ視聴のスタイルが従来と大きく変わる中、5年前の10月から、放送後にハードディスクレコーダーなど、録画機で視聴した数字も調査に加わることになりました。これが「タイムシフト視聴率」です。「タイムシフト視聴率」は、放送から7日(=168時間)以内に視聴したテレビ番組を調査します。具体的には、調査対象の世帯が、テレビのハードディスクなどに保存していた番組を7日以内に視聴すれば、タイムシフト視聴率のポイントが加算されます。タイムシフト調査が加わることで、リアルタイム視聴率との合算した数字も算出されるようになり、合算した数字から、タイムシフトとリアルタイムの重複分を差し引いた「総合視聴率」が公表されることになりました。ジャンル別に見ると、タイムシフト視聴率が高いのは「ドラマ」で、リアルタイムの数字は今一つなのに、タイムシフトの好調で、総合視聴率をグッと押し上げているコンテンツもあります。一方、スポーツやニュースはリアルタイムの独壇場で、ドラマに強い局、スポーツやニュースに強い局といったステーション毎のカラーが、より鮮明化されることになりました。このため、営業現場では自局の強みを再認識することにもつながり、局の長所を生かしたセールスが強化されました。
変化を強いられるテレビ広告
これまで、テレビの広告効果はブラックボックスに例えられてきました。統計上、どうしても標本誤差が出るため、あくまで「目安」にしかならない上、企業が打った広告効果を検証し辛く、実効性を疑問視するスポンサーも少なくありませんでした。こうした環境はインターネット広告の出現で大きく変わってきており、検索連動型あるいはアフィリエイトと呼ばれる成果報酬型の広告で、仕組みが透明されていることが、テレビ業界の意識を変えつつあります。そもそもテレビ端末そのものが、ネットワークにつながり、インターネット端末の一種になっている現在、テレビ広告が旧態依然でいられるはずはありません。
動画配信サイトの登場とテレビ業界の行方
こうしたテレビ業界の現状に新たな動きが加わっています。それが動画配信サイトの出現です。動画配信サイトの登場で、日本のテレビ局の対応は2極化しています。一つは定額制動画配信サイトと業務提携するケース。もう一つはライブストリーミング形式のインターネットテレビサービスを立ち上げ、広告ベースのプラットフォームを新設するケースです。このモデルは既に、ニコニコ動画などでも実現しています。ネットでの動画コンテンツは、視聴者に応じた広告の差し替えが可能ですが、テレビは技術的に、リアルタイムに流れる映像と広告を分離できませんし、ケーブルテレビなどの再送信の場合でも、法律上、元の放送に手を加えることは認められていません。つまり、ネットでの動画配信が進むにつれ、テレビ局のメリットだった放送設備の所有は、逆にフットワークの制約になっているともいえます。動画コンテンツ市場におけるテレビ局のポジションを維持するには、動画配信サイトの利点をうまく取り込みながら、コンテンツやノウハウの蓄積をはじめとしたテレビ局ならではの長所を伸ばしていくことが必要です。

視聴者層をより意識した番組制作
こうした変化は、既に番組制作の現場にも反映されています。どの層をターゲットにするのか、演出技術上はCMと番組本編の連動、さらにはスピンオフのネット公開など、枚挙に暇がありません。現場では、これまで以上に「より視聴者層を分析した内容」の番組制作が求められますし、スポンサーも枠をより意識することは論を俟ちません。この傾向は地上波やBSなどの放送本編よりも、スポンサーが視聴者層を特定してCMを打てる「動画配信サイト」や「見逃し配信サイト」で顕著になってくると想定します。如何にスポンサーの求めているニーズを汲み取り、それを番組にフィードバックさせていくか。これからの制作マンは、演出能力に加え、編成業務や営業の素養も必要十分条件と言えそうです。
テキスト:ナインフィールド
ディレクター 有明 雄介