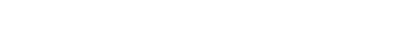テレビや映画といった映像作品で、音の占める役割が極めて重要なことは論を俟ちません。いわゆる「音まわり」について、収録から編集、番組化までを担当するのが、「音声スタッフ」です。ロケ番組で見かける長竿状のガンマイクを持ったスタッフや、スタジオでミキシングを担当するミキサーマン、さらには番組にピッタリな音をつくりだす音響効果など、様々なポジションがあります。番組上で音が出なければ、放送事故になりますので、ラジオなど音声メディアでは文字通りの生命線です。業界では「音声さん」「音屋さん」と呼ばれることが多いようです。今回はこの「音まわり」を担当する音声スタッフの仕事を紹介しながら、求められる人材像を探っていきます。

いろいろ呼び名はあるけれど…
音声スタッフとは、一言で言えば、テレビ番組の生放送や収録で、音響全般に関する技術的なサポートをする仕事です。スタッフを紹介する番組のエンドロールで「音響スタッフ」「PA」「サウンドエンジニア」「ミキサー」などと表示されますが、基本的には同じ職業です。収録にあたって使用するマイクの種類やポジションを決めたり、収録時の音のバランスを調整したり、映像作品の音声に関する編集を行ったりと、音声に関わるすべての仕事を行ないます。この他、少し分野は違いますが、ディレクターが執筆したナレーションや、実際の映像に合わせて、BGMや効果音、アタック音などをチョイスしていく音響効果を担当する場合もあります。これら「音回り」全般の担当者を現場では「音声さん」「音屋さん」と呼びます。
ロケ現場での音声さん
この「音声さん」収録現場では音声ミキサーなどの録音機材を使用して撮影時の録音を行ないますが、これがなかなかハードです。カメラマンに比べ目立ちにくい仕事ですが、音声がきちんと収録できていないと、番組として成り立たなくなるので、責任重大です。
では、具体的な中身を見ていきましょう。よく、ドラマやバラエティ番組で、先端にフサフサが付いた棒を掲げている人を見かけますが、あれは、ガンマイクという指向性の強いマイクを使って、スタッフが出演者や俳優の声を拾っています。「風防」と呼ばれるフサフサのカバーをつけることで、風を吸収してノイズを防ぎます。また、撮影中は、無駄な音が入ってこないか、必要な音が拾えているか、集中して確認する必要があり、気が抜けません。
これは実際にビデオカメラを回してみるとわかりますが、カメラマンが狙っているショットは、必ずしも音源も一緒にあるわけではありません。例えば、裁判の判決取材の際、カメラマンは被写体として「勝訴」と書いた紙を持って駆け下りてくる弁護士を追いますが、音はカメラマンの後ろに控える多くの支持者の歓喜の声にスポットを当てる必要があります。もちろん、カメラ内蔵のマイクでもある程度は拾いますが、基本、レンズを向けている方向と一緒なので、クリアには録れません。その点、音声さんを別立てすれば、カメラとは別の動きで音を収録できるので、収録の柔軟性が格段に拡がります。また、インタビューを受ける人の声が小さい場合、カメラマンが撮影中に音声レベルを調整するのは、かなりリスクを伴いますが、音声さんがいれば、その点も安心して任せられます。
さらに、撮影素材を編集に渡す意味でも大きな優位性があります。多くの場合、撮影の時点では、音のレベルがバラバラなので、そのままの音では編集の時に苦労しますが、ミキサーを使いながら現場で音のレベルをある程度揃えておけば、編集作業もスムーズですし、ストレスの軽減につながります。ただし、音声を上手く拾えるようになるには、ある程度の経験が必要です。場数を踏むこと以外、上達の近道はありません。
スタジオ収録の現場に欠かせないミキサーマン
一方、スタジオでの生放送や収録では、いわゆるミキサーマンが活躍します。現場によっては「音響オペレーター」や「PA」とも呼ばれ、ご記憶の方も多いでしょう。いわゆるスタジオでの音声の調整やマイクのセットなどを行なうのが主な仕事で、ミキサー業務をはじめ、場面や状況に応じて効果的な音を出すための技術が要求されます。地方局だと大抵一人ですが、在京キー局の場合、出演者や送出素材が多いので、主に音効・素材系とMC系でPA卓を振り分ける場合もあります。収録や生放送にあたっては、出演者の人数分のマイクはもちろん、有線かワイヤレスかの選択、さらには互いの音声が回り込まないようにマイクポジションを調整したり、VTRなどの素材音声についても、慎重に確認したりしていきます。
この他、在京キー局など大きな局には、MAミキサーと呼ばれる職種もあります。これは編集された映像に、ナレーションや効果音、SEなどをつけて音声の仕上げをする仕事のことで、スタッフロールでは「MA」とか「音響効果」と呼ばれます。換言すれば「音声演出」ともいえます。以前は、編集した素材テープから読みだしたタイムコードを頼りに、効果音やBGMを当て込んでいきましたが、映像素材がファイルベース化した現在では、コンピューターへ素材の音を取り込み、ミキシングマシーンや「PON」出しといわれるインスタントリプレイ装置を駆使して、映像に合わせて調整していく方法が取られます。この作業の場合、一人でこなすのが難しく、アシスタントが補佐をするケースもあります。もっとも、地方の場合は予算の都合もあって、大抵、ディレクターが編集時に一人でやってしまうことが多く、こうした専属職種が使えるのは、ドキュメンタリー大賞など、いわゆるコンテストものに限られます。
急速に進む機材進化の中で「音声」の役割とは
放送の黎明期はテレビ・ラジオを問わず、番組は全て生放送でした。ですから出演者のマイクも効果音もさらにはBGMもすべて生で進行してきました。「波の音」や「肝試しの火の玉の音」など、すべてが生出しで、失敗もありましたが、その分、おおらかでもありました。試行錯誤をする楽しさもあったと思います。やがて16ミリフィルムやUマチックと呼ばれるビデオテープが登場し、番組の収録が可能になるにつれて、編集の水準も高くなっていきました。いまでは全ての収録がファイルベースになり、映像はもちろん、音声分野でもPC上での「切り貼り」は当たり前になりました。加えて、動画投稿サイトの興隆で、何百万とする高級機材ではなくても、手持ちのPCで簡単に作品が作れるようになったことは時代の進化を実感します。こうした環境下、どの放送人にも言えることですが、特に「音声さん」には、動画投稿サイト全盛の時代、素人には真似のできない「プロの技」が求められているといえるでしょう。デジタル化が急速に進む中「音声」ならではのさらなるこだわりを追究するには、最新の機材を使いこなせる知識や技術が求められることはいわずもがなです。それでこそ、映像を深めるためのプロといえるのではないでしょうか。放送業界にもデジタルネイティブの世代がどんどん入り込んできている今、どんな作品を「魅せて」そして「聴かせて」くれるのか。ベテランの放送マンたちは新たな化学反応に期待しています。
テキスト:ナインフィールド
プロデューサー 笹木 尚人