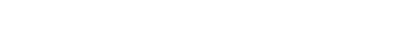テレビのワイドショーなどで、いわゆる芸能レポーターを見ない日はないでしょう。早朝の番組から午後、場合によっては夕方のワイドニュースまで出演し、その活躍は特に報道・情報系において欠かせない存在になっています。業務内容は、事件や事故などが発生した時に現場へ赴いて、現状や発生の原因、経過などを放送で伝えることですが、番組によっては、局へ帰らず、中継地点から中継地点へと渡り鳥のように動くレポーターもいて、フットワークや体力も求められます。今回はレポーターという職業にスポットをあて、誕生の経緯や詳細な業務内容、さらには求められる人材像など、その全貌に迫ります。

レポーター誕生の前夜
レポーターについてご紹介する前に、彼らの主戦場である「ワイドショー」の誕生経緯を簡単に振り返ってみましょう。日本のワイドショーの第一号は1964年の「モーニングショー」と言われています。ただ、当初はVTR技術がまだまだの時代。番組はスタジオトークを中心に、定時に新聞社が提供するニュース原稿を挟むというスタイルが中心でした。1970年代の半ばになると、各局は芸能ニュースを番組の核に据えるようになり、こんにちに続きます。もともとテレビにはレポーターという職制がなかったので、各局は週刊誌の芸能担当記者を、テレビ界へ引き抜き、「芸能レポーター」や「芸能デスク」といった肩書で現場へ派遣することになりました。その結果、各局にスターレポーターが何人も生まれ、レポーターから流行語まで誕生するなど、その存在は最早、社会現象と化していきました。
「芸能」から「事件事故」へ
当初は芸能ゴシップが主要コンテンツだったワイドショーも、80年代の初めになると、積極的に「事件事故」を報じるようになります。いわゆるニュースとの垣根が年々、低くなり始め、情報番組というカテゴリーながら、より強い報道色を志向するようになりました。これに合わせるように、レポーターの世界も、週刊誌の記者中心から地方局やラジオ局出身のフリーアナウンサーの進出が目立つようになっていきます。地方局ではアナウンサーが警察担当の記者を兼務することもあり、いわゆる「発生モノ」の現場に慣れていることが、大きな武器になりました。このようにレポーターの世界は、番組の変遷によって、求められるスキルが大きく変化してきた職種といえます。
レポーターの業務と求められる人材像
レポーターと聞いて、まず誰でも思い浮かべるのは、取材現場へ行って話題を取材し、放送できる形にまとめて伝えることでしょう。もちろん、その中には、政治家や芸能人など世間が注目する人々に対して、インタビューや取材を行なうことも含まれます。「芸能」「スポーツ」「ニュース」など、さまざまなジャンルの中で、レポーターは、その話題を一つの情報として簡潔かつ的確に伝えなければなりません。
ここで、必要になってくるのが、幅広い知識と情報収集力、正確に伝達する能力、さらには臨機応変に対応する力です。取材する現場や事件、話題、人などは実にさまざまですから、事前にいろいろ調べることができる場合もあれば、現場情報だけのぶっつけ本番という「スリル満点」の修羅場もあります。ここで大切なのは、臨機応変に対応できる素早い判断力を基に、取材先から最新かつ的確な情報を引き出したり、事実を細部まできちんと観察したりするなどの取材力といえます。これは報道、芸能、バラエティなど分野を問わず、必須のスキルです。
また、事件事故の場合は、時間や曜日、場所を選ばずに起こるため、すぐに現場に駆けつけるフットワークの良さや体力、それに精神力も欠かせません。加えてこうした「発生モノ」の現場の場合、最小限の人数で現場取材を行うチームが構成されているので、レポーターにも番組に関わるさまざまな仕事がまわってきます。現場のディレクターやカメラマンなどと連携して、原稿内容の精査やカメラアングルの把握なども担います。さらに生中継だと、決められた時間内にコメントを収めるというスキルも問われてきます。ここまでのレベルに至るには、現場の場数もさりながら、放送時間は少なくても、一つの情報伝達番組をみんなで作り上げていくという協調性が求められることは論を俟ちません。
番組の種類で決まる「求められる人材」
これまでいわゆる「専属レポーター」の役割を紹介してきましたが、ライバルもいます。従来から、ニュース番組では、報道部の記者や局アナがレポートを行う場合が多く、特に局アナはレポートの技術を問われる場面が多いです。一般にニュース番組は「局の報道スタンス」を問われてくるため、組織の外にいるフリーのレポーターは起用しにくいという事情もあります。一方で、クイズ番組のロケVTRなど、高視聴率を誇るバラエティ番組では、有名タレントや売り出し中のアイドルがレポーター役に起用され、番組の人気向上の大きな戦力になっています。番組ごとにオーディションが行なわれ、芸能プロダクションの中には随時、候補者を募集しているところもあります。ただし、この手の番組では、カメラ映りなど、レポート技術以外での要素が起用の決め手になることも多く、その分、出演者の新陳代謝は激しいともいえます。
こうした事情も手伝って、「職業=レポーター」という出演者は、従来のワイドショー中心のフィールドから、衛星放送やインターネット放送など、新しいメディアに活躍の場を拡げ始めています。
レポーターという職の将来
一般的には番組単位で契約するケースが多い専属レポーターですが、前門には「報道記者や局アナ」、後門には「タレントやアイドル」が待ち構え、より激しい競争にさらされ続けています。しかし、中には荒波を乗り越えて、生き残る人もいます。彼ら彼女らに共通して言えるのは、専門性や地域性を活かしている点です。例えば野球や相撲など、特定のスポーツに強ければ、局を問わずオファーは増えます。また、全国区のタレントを番組に呼べない地方局では、地域限定のタレントがレポーターとしてローカル番組の顔になっているケースも珍しくありません。ただし、彼ら彼女らはCMナレーションやイベントMCなど、レポーター以外の仕事も掛け持ちしています。首都圏や関西ならまだしも、地方都市ではレポーター専門で暮らしていくのは、なかなかハードルが高いといえるでしょう。
レポーターは、社会への影響力が大きな仕事です。自ら現場に足を運んでレポートするわけですから、スタジオにいる出演者では感じ取れない臨場感を伝えることができます。こうして放送した情報がきっかけで、ブームが起きたり、ときには世論が動いたりするなど、自分の仕事が社会に貢献できていることを実感できるのは、使命感を持って働ける要素の一つといえるでしょう。また「記者・局アナ」と「タレント」の中間に位置しているということは、双方の長所を採り入れて仕事に活かすことができるということでもあります。「堅すぎず、やわらかすぎず」個人のパーソナリティを活かしたレポートのできるレポーターが増えれば、「並み居るライバル」は、怖るるに足らずといえるのではないでしょうか。
テキスト:ナインフィールド
ディレクター 有明 雄介