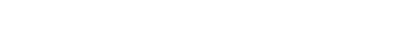先ごろ、将棋の藤井聡太七段がAIを使って、対局の研究をしているというニュースが話題を集めましたが、映像制作の世界でもAIを導入している作品は増えてきています。ムービーを自動生成してくれたり、字幕を自動でつけてくれたりする上、初心者でも簡単に扱えるので、普及のスピードは加速しています。今回はAIによる自動編集の現状を紹介しながら、メリットとデメリット、そして、AIとの共存が必須になっている生身のディレクターのあるべき姿などについて考察します。

驚異の進化を遂げる「AI編集ソフト」
YouTubeやTiktokなどのいわゆる動画投稿サイトの充実に伴い、所謂、「実写」のカットをつなぐだけの機能から、被写体の加工へと投稿者の要望が移ってきています。これを可能にしたのが、「AI編集ソフト」です。
すでに、一部の大手企業が先行導入している「VIDEO BRAIN」は、写真や動画などの素材を入れて、作りたいフォーマットを選ぶだけで、あとはAIにおまかせという優れモノで、素材を自動で分析し、高品質で最適な動画が完成します。
「ニュース」や「SNS広告」、「サイネージ用動画」など、目的に合ったフォーマットを選択。BGM素材をはじめ、音声データをAIが分析してテロップを自動で挿入する機能まで揃っているので、テキストでの書き起こし作業が省略でき、このツールだけで簡単に動画編集ができます。
他にも、動画編集Adobe Premiere Elements 2019では、AI技術を活用し、写真や動画の整理から編集などを自動で行う機能を備えている他、SNSやDVDなど、さまざまな共有方法が選択できるなど、充実しています。これらは全てAIに関連する先端技術「ディープラーニング」=深層学習がベースになっています。
AIカメラがスポーツコンテンツの市場を拡大
放送現場へのAI導入も、想像をはるかに超えるスピードで進んでいます。イスラエルのPixellotが販売しているAIカメラと関連サービスは、スポーツの試合を自動的に撮影し、中継用映像の編集まで仕上げます。
Pixellotのカメラは、数台のカメラを積み重ねて円筒形にしたような「ユニークな形」をしていて、全体が見渡せるよう、コートやフィールドなどの中心付近に設置されます。この複数のカメラが撮影を同時に開始し、競技会場全体を8Kの映像として収録。単純に対象となる領域を撮影だけでなく、プレーヤーやボールなど、重要なプレイが行われている場所を追跡することもできます。
撮影されたデータは、Pixellotのサーバーに転送され、そこでAIが適切な編集を実施。まるでプロのカメラマンが中継しているかのようなコンテンツを作り上げます。
必要があれば、その際に試合の経過時間や両チームのスコアといった関連情報も提供する他、各種端末への配信機能も備えていて、フィギュアスケート、サッカー、バスケットボール、ラグビー、バレーボール、それにレスリングや体操など、対応競技は12にも上ります。
さらに、Pixellotでは、従来の手法で制作した場合と比べ、9割の以上のコストを節約できるとしていて、これまで採算面から対象にならなかったマイナーな競技や試合をはじめ、一般人が市販のビデオカメラやスマートフォン数台で撮影していたアマチュアスポーツでも、積極的に映像化と配信が行われる可能性も現れています。
人間に代わってAIが大量のコンテンツを制作し、配信まで全自動で行うようになりつつあることで「新たな映像の世紀」はさらに進化し、より多くの出来事が単なる映像ではなく、ハイクオリティなコンテンツとして楽しまれるようになっていく時代が到来しています。
人対AI…感情の有無が作品の出来を左右する
さまざまな職業で「AIが人間から仕事を奪うのではないか」とささやかれている中、カメラマンや映像編集者もその危機に瀕しています。前述のPixellotも、撮影された映像から試合の見どころだけを抽出して、ハイライト映像を作成するという機能も提供していますし、さらに驚きなのは、競技や試合の中断を自動で認識し、視聴者の邪魔にならないようにCMを入れるという機能さえ備えています。AIが常に進化し、高度な能力を獲得していく中、映像作品においても、一定のクオリティのものはできるかもしれません。
ただ、こうしたAI編集には当然、感情がありません。その分、意外性や雰囲気、それに個性といったものは期待できないと言っていいでしょう。ディレクターは普通、撮影した映像素材を編集する際、視聴者が「慣れる」「飽きる」ことを意識しています。どんな「敏腕ディレクター」でも、気持ち良い映像だけを流し続けることはできないので、構成の中に「ワビサビ」をつけ、映像に関する視聴者の感情の起伏を想像しながら、編集します。そのためには、敢えて「無駄」を入れる場合もあります。
先述のように、選手やボールを追うようなスポーツであれば、AIでも、ある程度のクオリティは保たれるでしょうが、おそらく「無駄」の要素が必須なバラエティやドキュメンタリーでは、全く意味不明のものができてしまうかも知れません。換言すれば、「無駄」を含めたディレクターの創造性が、テレビや動画を楽しくさせているともいっていいでしょう。
仮にAIがメインになったとしても、映像の入口と出口については、ディレクターが指示するなど、AIに作らせたものに生身のディレクターがさらに関与することが、作品の質を向上させるベストな選択といえるのではないでしょうか?

機械を扱うのも人間。人の気持ちが伝わる編集…。
確かにAIの進歩は、放送の現場に大きな変化をもたらしています。しかし、これらはあくまで「道具」であり、扱うのは人間です。生身のディレクターが、文明の利器を自在に扱い、そこに、「人が感じる息吹」を吹き込んでこそ、共感を呼ぶ作品が完成することは論を俟ちません。AIの普及がカメラマンやディレクターの職を奪うかも知れないという話題を先述しましたが、経験と感性が豊かなディレクターの手掛ける映像は、おそらくテクノロジーの英知を結集しても、きっと敵わないでしょう。
加えて、これからの映像制作には、AIを「どう使うか」ではなく「何に使うか」を考えることが、かなり重要な要素になってくるでしょう。前述のPixellotのような技術を駆使して、人間だけでは不可能なもの、あるいは足りないものに、積極的にAIを活用していきつつ、肝心なところには、生身のディレクターの感性を存分に盛り込んでいくことが、より多くの視聴者の共感につながることは論を俟ちません。
特にAIでは表現や思考が不得手な「喜怒哀楽」は、やはり生身の作り手の関わりが不可欠です。なぜなら「報道」「スポーツ」「バラエティ」「ドラマ」とジャンルの別を問わず、映像制作は「エンタテインメント」の要素を備えていて、作品を通じて、人の情に訴える仕事だからです。
ツールをライバルとして捉えるのではなく、生身のディレクターが、AIを上手く活用する「論理的知能」と、AIでは実現できないウィットにとんだ感覚を伴わせることが、これからは必要になってくるのではないでしょうか。言い換えれば、自身の感性の表現のために使いこなす「スキルとメンタル」を身につけることが、令和時代のディレクターに求められている「必要十分条件」であることは間違いなさそうです。そういう集団が揃っている会社こそが、これからの業界の淘汰の荒波に生き残っていくのだと実感します。
テキスト:ナインフィールド
ディレクター 高橋 孝太